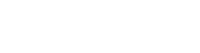- 2024.12.16
- 「すげの里の冬支度」その2
- 2024.11.26
- すげかのお正月準備
- 2024.11.12
- 「すげの里」の冬支度
今日は、職員ミーティングの日です。薪ストーブのガードを、例年、この時期に設置しており、利用者の皆様が心地よく里山体験ができるよう設置しました。
「すげの里」は、自給自足による里山の暮らしを参考に、エコで自然にやさしい循環型の暮らしを意図して薪ボイラーや薪ストーブ、太陽光発電などを導入しています。
薪ストーブは「暖かくて、火もちが良い広葉樹(サクラ・カシ・クヌギ・コナラなど)を使っています。着火用には、針葉樹(ヒノキ・スギ)を使っています。
利用者の皆様からは、「結構、温かいね。」「二階で寝ていても、温かかったよ。」など、うれしいお声を頂いています。
冬の里山も、良い所ですよ。是非、体験してくださいね。
「すげの里」は、自給自足による里山の暮らしを参考に、エコで自然にやさしい循環型の暮らしを意図して薪ボイラーや薪ストーブ、太陽光発電などを導入しています。
薪ストーブは「暖かくて、火もちが良い広葉樹(サクラ・カシ・クヌギ・コナラなど)を使っています。着火用には、針葉樹(ヒノキ・スギ)を使っています。
利用者の皆様からは、「結構、温かいね。」「二階で寝ていても、温かかったよ。」など、うれしいお声を頂いています。
冬の里山も、良い所ですよ。是非、体験してくださいね。
- 2024.11.7
- 「すげの里」の環境整備
環境整備は「すげの里」を維持管理していくための大事な仕事の一つです。
また、利用者の方が、気持ち良く利用して頂くための仕事でもあります。
今回の環境整備は、木の伐採をしました。
「すげの里」は平成23年5月に開館し、今年で13年経ちました。
建設時に、入口の右手に1mの木を植えました。その木も今では約8mにもなったことから、豊田市道(足助菅田和切山西樫尾線)から「すげの里」が見えにくくなっているとの意見がありました。
協議した結果、伐採したほうが「すげの里」の存在をよりアピール出来るとの結論に至り、伐採となりました。
また、利用者の方が、気持ち良く利用して頂くための仕事でもあります。
今回の環境整備は、木の伐採をしました。
「すげの里」は平成23年5月に開館し、今年で13年経ちました。
建設時に、入口の右手に1mの木を植えました。その木も今では約8mにもなったことから、豊田市道(足助菅田和切山西樫尾線)から「すげの里」が見えにくくなっているとの意見がありました。
協議した結果、伐採したほうが「すげの里」の存在をよりアピール出来るとの結論に至り、伐採となりました。
「あの建物、何だろうね?ちょっと寄ってみようかな?」なんて声が聞こえてきそうです。
利用者の方が「里山を体験できて良かった。いい所だね。また来たい。など」と言って貰えるよう、今後も、職員一同、頑張ってまいります。
利用者の方が「里山を体験できて良かった。いい所だね。また来たい。など」と言って貰えるよう、今後も、職員一同、頑張ってまいります。
- 2024.10.12
- 秋めく10月
小川のそばにピンクの小さな花が咲いていました。
見たことはあるけど、名前を知らない植物ってたくさんあります。どなたでもご利用いただけるすげの里の本棚にあった図鑑で調べるとミゾソバの仲間のようでした。
コスモスなど秋のお花と一緒に飾っていますのでご覧くださいね。
見たことはあるけど、名前を知らない植物ってたくさんあります。どなたでもご利用いただけるすげの里の本棚にあった図鑑で調べるとミゾソバの仲間のようでした。
コスモスなど秋のお花と一緒に飾っていますのでご覧くださいね。
自然の景色に癒されながら、職員宅の庭でたくさん採れたローゼルで作ったお茶、ジャム、塩漬けの試食会をしました。少しの酸味と、鮮やかな赤色が華やかです。
最近、産直の野菜などの中にもローゼルをよく見るようになってきました。すげの里に来られた時は近くの産直などをのぞいてみるのも楽しいかもしれません。
最近、産直の野菜などの中にもローゼルをよく見るようになってきました。すげの里に来られた時は近くの産直などをのぞいてみるのも楽しいかもしれません。